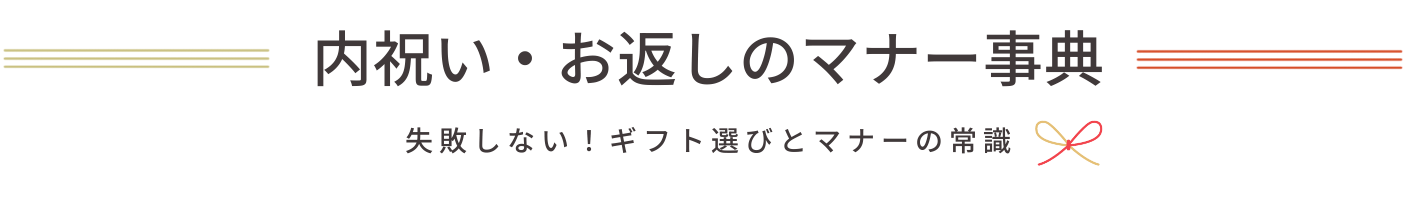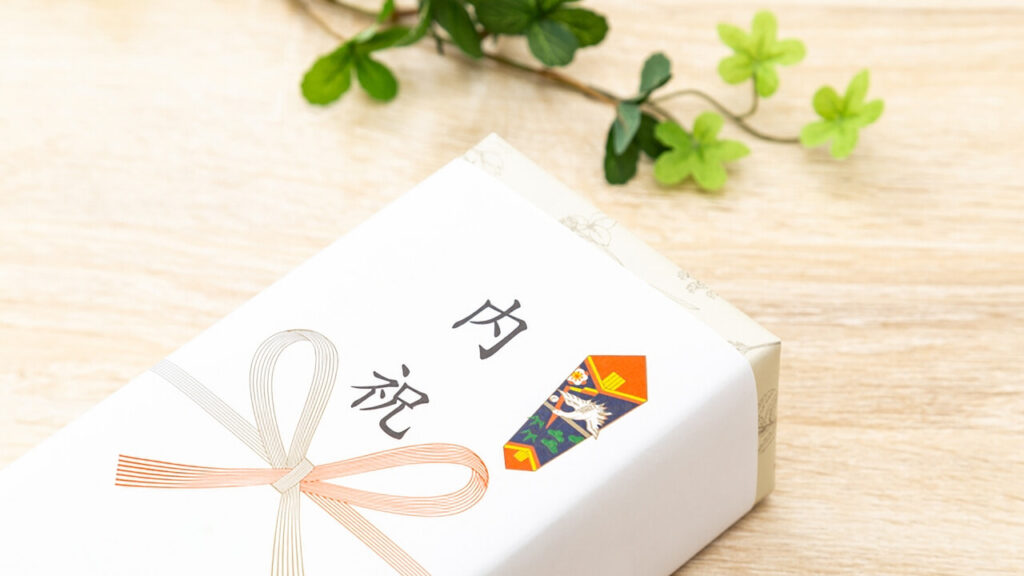Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48
Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48
Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

内祝いやお返しは、時期を逃さず贈りたいものですが、どうしても都合が悪かったり、遅れてお祝いをもらったり、お礼をする時期が遅くなることがあります。
ここでは、内祝いやお返しが遅くなったときの、お礼の仕方をまとめています。思いやりのある内祝いやお返しになるように心配りをしましょうね。
内祝いを渡しそびれてしまったら

内祝いを渡しそびれたからといって、お返しをしないというわけにはいきません。時期を逃して遅くなったとしても、お礼の品物はちゃんとお返しするようにしてくださいね。
お祝いを贈ったのに何の連絡もなく、忘れた頃に品物だけが届いたら、「いまさら?」と思う方もいますので、お礼状に遅れたお詫びの言葉も一言添えて、お返しの品物と一緒に感謝を伝えるようにしましょう。
このとき、遅れた理由をはっきりと書く必要はないですが、「お礼が遅くなってごめんなさい、いつもお気遣いいただいてありがとう」と、日頃からの感謝の気持ちも添えると相手は嬉しいものです。
お返し忘れてた!!と気が付いたのなら、今からでも準備を初めて早めに内祝いを贈ってくださいね。
[colored_bg color=”light‐red” corner=”sq”]
check!
出産内祝いの場合は、遅れたとしてもマナー違反にはなりません。赤ちゃんのお世話やママの体の回復にも時間がかかりますから、皆さんわかっているでしょう。けれど、お返しのときには一言、遅くなったお詫びは伝えましょうね。
[/colored_bg]
遅れてお祝いをもらったときのお返し
お祝いを遅れてもらったときは、その都度お返しをするようにします。「遅れてもらったからお返しはいらないよね?」という方がいますが、遅くなったお祝いでも他の方と同じようにお返しをお渡ししましょう。
「遅れてしまったけれど祝ってあげたい」という相手の温かな気持ちですから、早めにお返しをするようにしてくださいね。
相手や自分が喪中のときのお返しの時期

喪中である期間は、祝い事は避けて慎むべきと昔からいわれていますので、いつ内祝いやお返しをすればいいのか悩みますが、現代では喪中でも気にせず、都合のいいときにお返しされる方もいるようです。
お歳暮やお中元などの贈り物は、内祝いとは違って祝い事の贈り物ではないので、相手が喪中期間であっても失礼にはなりません。
[colored_box color=”light‐gray” corner=”sq”]
自分が喪中のとき
自分が喪中のときに内祝いを贈っても問題はないですが、喪中のご家庭から品物が届くことを気にする方もいます。贈る相手を考えて、喪が明けてからお返しするか時期を判断しましょう。
喪が明けてからお返しするときは、「喪中であったためお礼が遅くなり失礼しました。」と一言添えると、相手もわかってくれることでしょう。
[/colored_box]
[colored_box color=”light‐gray” corner=”sq”]
相手が喪中のとき
相手が喪中であるときは、四十九日を待ってからお返しをするようにします。先方は何かと慌ただしくしていますから、心配りをするようにしてくださいね。
[/colored_box]
喪中のときの熨斗の表書き

喪中のときの熨斗(のし)の表書きは、「内祝い」ではなく「御礼」として贈る方が適しています。
内祝いを渡すお日柄は気にする?
参拝や結婚式などのお祝い行事では、お日柄を気にする方は大半です。結婚招待状の返信はがきなどの消印も、「大安」や「友引」にするなど、心配りをされる方もいらっしゃいますが、「その日に受取ができなければ意味がない」と、お日柄は特に気にしないという声も多くありました。
気にするか気にしないかは人それぞれのようですが、お日柄のよい日に内祝いやお返しを贈ってあげると相手も嬉しいものですね。
お日柄(六曜)
[colored_box color=”light‐yellow” corner=”sq”]
大安(たいあん)
何をするにおいてもよい1日。
[line color=”light‐yellow” style=”dotted” width=”1″]
友引(ともびき・ゆういん)
何をするにも勝ち負けが付かない一日
友を引くと解釈できるため、弔事を避ける日。
[line color=”light‐yellow” style=”dotted” width=”1″]
先勝(せんしょう・さきかち)
午前中が吉、午後から凶
[line color=”light‐yellow” style=”dotted” width=”1″]
先負(さきまけ・せんぷ)
午前は凶、午後から吉とされている。
[line color=”light‐yellow” style=”dotted” width=”1″]
赤口(しゃっこう・せきぐち)
正午(昼)は吉、午前と午後は区。
[line color=”light‐yellow” style=”dotted” width=”1″]
仏滅(ぶつめつ)
何をするにもよくない1日ですが、弔事はかまわない。
[/colored_box]
行事別のお返しの時期
[/check_list]
[/check_list]