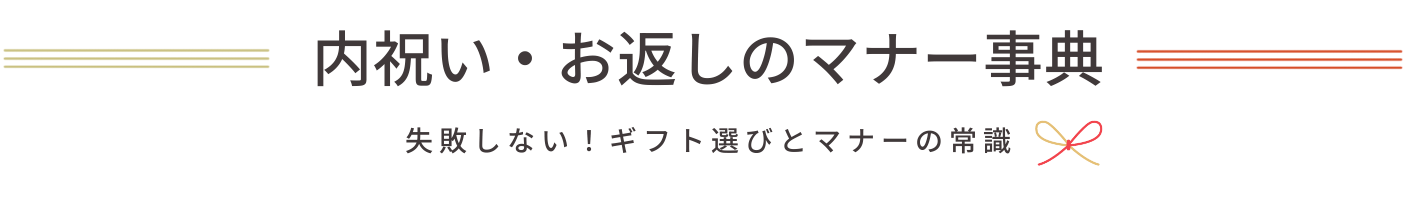Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48
Warning: Undefined array key 0 in /home/st-candle/okaeshimanner.com/public_html/wp-content/themes/keni80_wp_standard_all_202311082357/keni/module/keni-shortcode/keni-shortcode.php on line 48

帯祝とは、妊娠5ヵ月の戌の日に腹帯を巻いて安産祈願をする儀式で、ママのお腹の冷えの防止や赤ちゃんを保護するだけでなく、「元気な赤ちゃんが産まれますように」と願う日本のすばらしいしきたりです。
帯祝いでは、義母や実家からお祝いをいただくことがあります。そんなときのお返しについてまとめています。
[faq_q color=”red”]戌の日というのはなぜ?[/faq_q]
[faq_a]
日本では、歴を干支を使って表します。干支の一つである「戌」は、12年に1度めぐってきますが、年号と同じように日付も12日間ごとに干支を使って表します。ですから1ヵ月に戌の日は、2~3回おとずれることになるのです。
どうして戌なのかというと、犬は安産で子供をたくさん産むことから、これにあやかって祈願するようになったのです。[/faq_a]
お返しは必要なの?
基本的に、帯祝いをいただいたときのお返しは不要ですが、家族を自宅に招き食事を振る舞ったりして、お礼をされる方もいます。
身内からのお祝いは「お返しはいらないから」といわれることもありますが、金額にこだわらず義母や母親が好きなお菓子などで、お返しされると喜ばれると思います。
家族以外の方にお祝いをもらったのなら、今後のお付き合いもありますのでお返ししたほうがいいですね。
また、内祝いとしてお赤飯や紅白餅などを配る地域もあります。内祝いの仕方は、お住いの地域によって違いがあるので、わからないときは両親や地域の風習に詳しい方などに相談されると安心です。
どんなときでもお祝いをいただいたのなら、電話やお礼状で感謝の気持ちを必ず伝えるようにしたいですね。
お返しの時期と金額
昔は参拝後、自宅に招いてご馳走を振る舞いみんなでお祝いをしていましたが、現代では仕出しをとったり会食される方が多いようです。その場合、お礼として食事代を負担するのもよいでしょう。
お菓子など品物でお返しされるなら、金額の目安は1/5~1/3が一般的のようです。1週間から1ヵ月以内に内祝いとして贈りましょう。
水引の選び方と熨斗の表書き

帯祝いの内祝いでは、紅白蝶結びの水引を選びます。
のし紙の上の書き方
「帯掛内祝」「内祝」「御礼」
のし紙の下の書き方
姓、または姓名